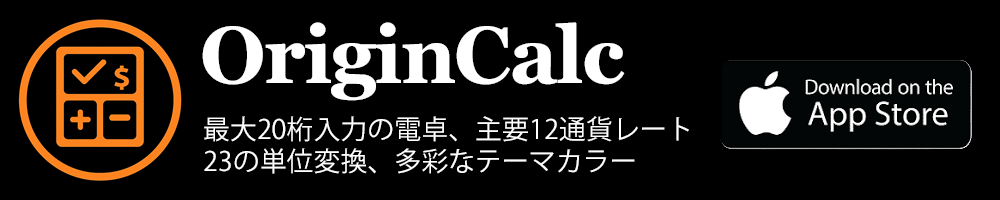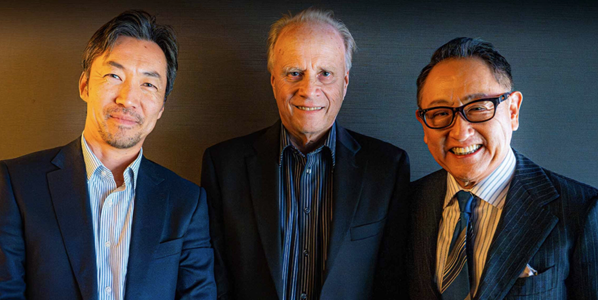レッドブルのドライバー選定は、いつの間にか「優秀なドライバーを擁し恵まれた環境」での選択から「苦渋の選択」へと様相を変えている。残るのはレッドブルの1シートとレーシングブルズの2シート、計3席だ。候補は角田裕毅、リアム・ローソン、イザック・ハジャーという将来性と即戦力を兼ね備えた面々で、評価材料が積み上がるほど結論は遠のく構図になっている。
決断を難しくしている一つの要因はローソンの躍進、再評価であり、混戦を読み切る集中力と一発の速さに説得力を手に入れた。一方で角田は、予選・決勝を通じた安定度、パッケージ理解、タイヤマネジメントに裏打ちされた総合力を手に入れつつあり、レーサーとしての資質と開発貢献を示している。さらにハジャーはF2実績とF1での順応性で存在感を増し、2026年の新規則を見据えた先物買いの誘惑を強めている。
また他にもリンブラッドなど、チャンスを与えたい若手が控えているが、若いドライバーを起用して直ぐにF1で活躍を見込むことが難しくなっていることは、過去の多くの経験から学んでいるはずだ。これ以上過ちを繰り返せば、レッドブルF1をドライブしたいと思う若手ドライバーは市場から居なくなってしまう。
問題の核心は「席は3つ、候補は3人以上」という単純な算数に収まらない点だ。フェルスタッペンのタイトル挑戦を支える経験値、マシン開発に効くフィードバック、次期規則への適応力、ブランドの物語性までが評価軸となり、焦点は誰をどこで活きるかという最適配置に移る。理屈だけなら、レッドブルに即戦力(角田かハジャー)、Racing Bullsに伸びしろ重視(ローソン+もう一人)という絵が浮かぶが、待てば待つほど難しい材料が増える。どのストーリーを選んでも、ひとつの「もしも」は必ず残る。レッドブル内の議論は、日を追うごとに難しくなっているに違いない。