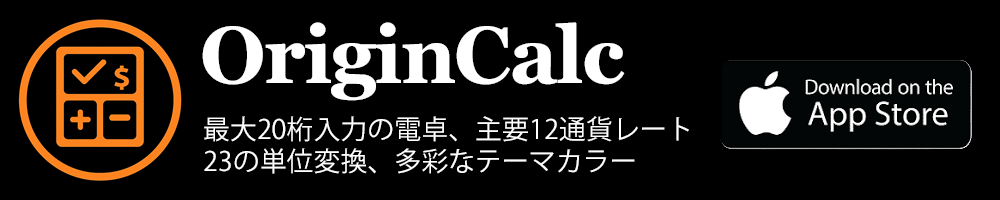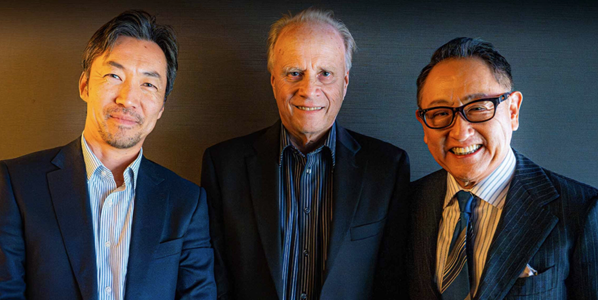ジャック・ドゥーハンによる日本グランプリ(FP2)のクラッシュをきっかけに、現状はドライバーの操作によって制御されているDRS(ドラッグ・リダクション・システム)について、これを自動化すべきかどうかという点で、ドライバーたちの間で異なる意見が出ている。
ドゥーハンは1コーナーに差し掛かる際、DRSがオープンになったままターンインして制御を失い、タイヤバリアに激突。アルピーヌA525は大破を喫した。チームの発表によれば、これはドゥーハンがDRSオフの操作をしなかったことに起因しているという。
現在、DRSはドライバーがボタンを操作するか、ブレーキを踏むか、あるいは一定量アクセルを緩めるオフにしなければならない。しかし、こうした手動操作が危険すぎるのではないかという懸念の声も上がっている。シャルル・ルクレールは、DRS自動オフの導入に前向きな意見を述べた。
「もしそのようなシステムが存在するのであれば、我々はそれを利用できると思うし、シルバーストーンの第1コーナー手前のように、もっとDRSを活用できる可能性があると思う。ここ(鈴鹿)の130Rのような長いストレートがあるのに、それを活用できないのは少し残念だと思う。」
カルロス・サインツもDRS自動オフに賛成している。
「安全性は、常に最優先されるべきだ。特に、今のF1カーが到達するような高速域では、それがなおさらだ。過去のF1なら、ジャックは今日無事ではいられなかっただろう。だからこそ、我々は安全性に関して進化し続けなければならない。現在のような超高速マシンにしていくのであれば、それに見合う安全対策が必要だ。
僕は金曜日の時点で、こうした事故がもっと起きていてもおかしくないと感じていた。自分でもDRSボタンを誤って押してしまい、開いたままターン1に突っ込んでしまって、激しいスナップと恐怖を感じたことがある。上海のターン1、オーストラリアのターン9など、同じような例がたくさんある。」
「こうしたクラッシュがあまりに発生していないせいで、安全性向上の必要性が証明されていないように思える。
だが、今回のドゥーハンのクラッシュを機に、ブレーキングの100メートル、50メートル前には自動でDRSが閉じるようにすべきだと証明されることを願っている。そうすれば、ドライバーのミスやDRSの閉じ忘れによる危険が未然に防止できる。」
「自動でDRSを閉じなかった場合にも、ドライバーに警告が出るような仕組みが必要だ。来年、ダウンフォースの調整が行われる予定がある中で、この問題に対して何らかの自動化されたシステムを導入することが我々にとって重要だと思う。」
一方、ジョージ・ラッセルは、自動化に反対するコメントをしている。
「ジャックに起きたことは非常に大きなクラッシュで、不運な出来事だったが、これはF1のカレンダーの中で唯一、問題が発生するようなコーナーで起きたことだと皆が認識する出来事になるだろう」と、メルセデスのドライバーは語った。
「ドライバーとしての責任がある。ストレートでは全開で走り、コーナーに向かって進入しながらDRSをオフにするボタンを押すのも仕事の一部だ。自動化は望まない。我々にはすでにあまりにも多くのガジェットが存在している。」
「DRSのオン/オフ操作」に個人差があり、それがタイム差として表れるようなテクニックであれば、手動のままにすべきだが、どのドライバー操作しても同じなのであれば、自動化して誤操作を防ぎ、安全性を優先すべきだろう。「ドライバーがDRSを操作する」部分は、ドライビングテクニックの面でも、自動車の技術革新の面でも、またスポーツエンターテイメントの側面においてもF1の何かを損なうことはないようにみえる。
※4.12 アロンソ、フェルスタッペン、アルボンのコメントを追加
フェルナンド・アロンソ:「私はそれについて強い意見を持っていない。どちらの意見も正しいと思う。シルバーストンと同じようなものだと思っている。ターン15では、DRSを開いたままコーナーに入ることになるので、自分で閉じるか、開けたままコーナーに進入するかを選ばなければならない。ただ、鈴鹿は非常にユニークなサーキットであり、あのクラッシュも少し特異なものだった。来年には変更が入る予定で、車両側でDRSのドラッグ削減が半自動的に行われるようになるので、この話題自体がなくなるはずだ。
いくつかの車にとっては、130RでDRSを開けたまま予選を走ることが可能だが、他の車にとってはそれが難しい場合もある。それは、DRSがサーキット全体で自由に使えた過去にも同じことが言えた。レッドブルはシルバーストンのターン1とターン2をDRSを開けたまま走行していたが、他のチームにはそれができなかった。
これがF1というスポーツの普通のことであり、ある車ができることを他の車ができないこともある。そして、我々がFダクトを使って片手で運転していたようなトリッキーなデバイスもあった。このスポーツの本質は、毎週新たな限界を探求することにあるので、それもF1にとっては良いことだと思う。
我々はもっと自由に決断すべきだと思っているが、実際には多くの決断において十分に自由ではない。アウトラップの準備や予選、エネルギーのデプロイメントなど、今は自動化されているが、以前はステアリングホイールにある6秒間使用できるボタンを戦略的に使いたい場面で活用していた。それによって、オーバーテイクのための異なるスポットが生まれたり、戦略に変化が生じたりしていた。今は、すべてが同じストレートで同じエネルギーを使うようになってしまい、自由にオーバーテイクや戦略変更ができなくなっている。それはもう十分だと思っている。」
マックス・フェルスタッペン:「経験豊富なドライバーであれば、ターン1に進入する際にDRSを閉じなければならないことを理解している。なぜなら、まだ全開でそのコーナーに進入しているからだ。おそらく、あれは経験の問題だったのだろうと思う。来年には、自動的に閉じるような“フレキシブルDRS”とでもいうべきものに変わるはずで、そうなれば自然と閉じるようになるだろう。私はそのような規制は来年のためのものであり、今シーズンに関してはそのような自動的なDRSの閉鎖タイミングや位置の指定は必要ないと思っている。」
アレクサンダー・アルボン:「自分はこの議論の中心にはいないが、来年について言えば、あの“フレキシブルDRS”のような技術にどれほど依存することになるのかを考えると、何らかのシステムは必要だと思っている。
これは非常にユニークな状況だと思うし、一方でそれを“スキル”とも見なせるが、不必要なリスクでもあるとも感じる。例えば日本を見てほしい。オーバーテイクが少ないと我々は不満を言っているが、DRSゾーンを追加することは容易にできるはずだ。シルバーストンも同じで、コーナーがあるからDRSゾーンを追加していないというのが理由だと思う。
しかし、実際には中国のターン1や鈴鹿のターン1のように、手動でDRSを閉じることが行われているならば、それでもDRSゾーンをもっと追加すべきだと思っている。
もし自動化されたシステムを追加できれば、FIAやF1はより安心してDRSゾーンを増やすことができるのではないかと思う。純粋なレーススタイルではないかもしれないが…。
日本では必要ないかもしれないが、例えば130Rの手前に配置するのではなく、ターン11の出口に配置すれば、DRSが連続して配置されたとしてもターン1で自動的に閉じるようなことは避けられるはずだ。これが私の考えだ。」