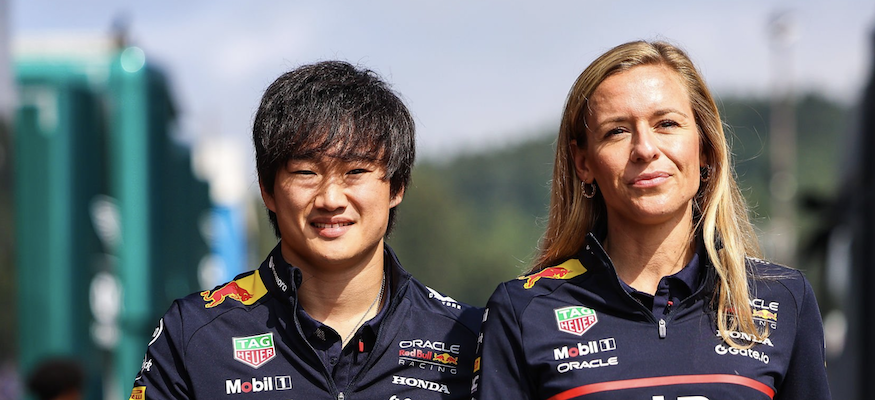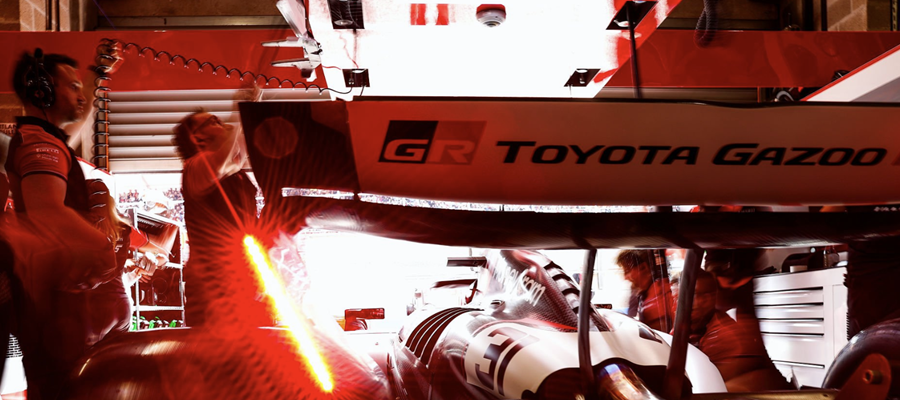F1日本グランプリで、マクラーレンは戦略面において再び注目を集める展開となった。予選ではレッドブルとマックス・フェルスタッペンにごくわずかな差で敗れたが、2台のマシンを活かすことでレースで逆転できる可能性もあったようにみえた。
日本GPで最も特徴的だったのは、レース展開の鍵となるはずだった“タイヤデグラデーション(劣化)ゲーム”は起きなかったことだった。鈴鹿サーキットの新舗装が1ストップ戦略を導き、マクラーレンの武器になったかもしれないタイヤマネジメントのアドバンテージは消えてしまった。
ジョージ・ラッセルがピットインしたことで、マクラーレンはオスカー・ピアストリを先にピットへ呼び入れてラッセルをカバーする決断を下した。その後、チームには2つの選択肢しか残されていなかった──フェルスタッペンと同じ周にピットインするか、あるいは現スティントを延長するか。結果、マクラーレンは2台同時にピットへ向かわせる戦略を採った。
この判断を行った瞬間、ノリスとピアストリはフェルスタッペンをコース上で追い抜くしか勝つ道は残されないことになった。マクラーレンのマシンがあれば可能にみえたこのミッションも、実際には非常に困難なものであった。
マクラーレンのチーム代表アンドレア・ステラは、追い抜きのためには0.7~0.8秒のペース差が必要であったと説明している。ペースの違いがほとんどなく、タイヤの状態も最後まで良好であったことから、マクラーレンは2位と3位を受け入れざるを得なかった。
またピアストリをノリスの前に出すことで、フェルスタッペン攻略のチャンスを生む案もあったが、この選択肢は採られなかった。ステラはその理由について、ピアストリが明確なペース優位を持っていると確信できなかったとコメントした。
ノリス:「もちろん、事前にいくつかの計画を立てていて、ある程度何が起こるかは分かっていた。でも、“後知恵”というのは素晴らしいもので、もっと長く走るべきだったか、もっと早くピットに入るべきだったか、なんてことも考えられる。でも、仮に3周前や2周前にピットに入っていたら、その後にセーフティカーが出た場合、我々はバカに見えてしまう。だから、すべてを完璧にこなすのは無理なんだ。それを受け入れるしかない。
改善すべきエリアはあると思う。高速域では非常に強く、間違いなく最速だった。一方、低速ではレッドブルに大きく劣っていて、それが昨日の予選での敗因だった。今日のレースでもその傾向は変わらなかった。だから、まだまだ改善すべきポイントは多い。」
ピアストリ:「もちろん、望んでいた結果ではなかったが、ペースやレース運びに関しては満足できるものだったと思う。昨日の予選でパフォーマンスを出し切れなかったことが、今日の展開にも大きく影響したのは明らかだ。それが今回の結果につながっていると思う。
ピットストップのタイミングに関しては、ラッセルが1周前にピットに入っていて、ルクレールもそれほど離れていなかった。アンダーカットがどれほど効果的かもわからなかった。中盤までミディアムタイヤで十分に走ったし、僕としては明らかに間違ったことをしたとは思っていない。そして終盤では、自分の感じたことを伝えた。
チームは現状に満足していたようだ。もし僕がノリスの立場だったら、同じように満足していただろう。それで構わない。自分の感じたことを言葉にしただけだ。それが僕たちのレースのスタイルなんだ。」
ステラ:「ノリスを先にピットさせるという選択肢もあったが、それをやるとピアストリをピットに入れられず、それが彼にとって大きな問題になったはずだ。とくにラッセルのようにすでにピットを終えたマシンをカバーする必要があったため、ピアストリを待たせるわけにはいかなかった。
ドライバー2人とも、昨日の予選Q3で最高のラップを出せなかったことは自覚していると思う。マックスがあれだけレベルを引き上げた中で、予選では1ミリ秒単位でラップを仕上げる必要がある。実際、P3とP1の差は0.043〜0.045秒というわずかなものだった。今回のようなレースで勝つには完璧な実行力が求められる。予選の時点で0.1~0.15秒の優位性を感じていたが、最後のQ3ではそれが失われていた。
誰もが“あそこでこうすればよかった”と言いたくなるが、それこそがミリ秒の世界だ。しかし、この数ミリ秒の差で週末全体のポジティブさが見失われるべきではない。ドライバー2人にとっても、チームにとっても、チャンピオンシップ争いにおいては重要なポイントを積み上げた。マックスとレッドブルを倒すには、最高のレベルで、しかも継続的に戦わなければならない。今回は勝てる可能性がありながらも2位と3位だったが、それは堅実なレース運びであり、シーズンの終わりには必ず実を結ぶと信じている。」
チームオーダーでフェルスタッペンを抜けたか?
ピアストリ:「正直なところ、難しすぎた。あと100メートル直線が長ければ、わずかなチャンスはあったかもしれない。でも、何度か近づいたものの、実際に仕掛けられるほどではなかった。ペースは良かったが、それでも決定打にはならなかった。ダーティエアの影響もあり、これ以上接近するのは本当に困難だった。だから、現実的には何かが起こる可能性はとても低かったと思う。」
ステラ:「オスカーの方が速かったとは明確には言えない。ランドはマックスのスリップストリームに入るために接近しようとしていたが、1秒以内に入ると著しいグリップの低下が起こった。だから、ランドは一度離れてタイヤを冷やしてから再び近づこうとしていた。したがって、表面的なペースだけで判断するべき状況ではない。フェルスタッペンに最大限の勢いで接近しようとしたが、難しかった。
最初から分かっていたことだが、このサーキットでオーバーテイクするには0.7~0.8秒の性能差が必要だ。それだけのラップタイム差は、通常タイヤの劣化から生まれるが、新舗装によって鈴鹿は高デグラデーションサーキットから低デグラデーションサーキットへと変貌を遂げた。今回は非常にシンプルな1ストップ戦略であり、戦略の幅がほとんどなかった。」