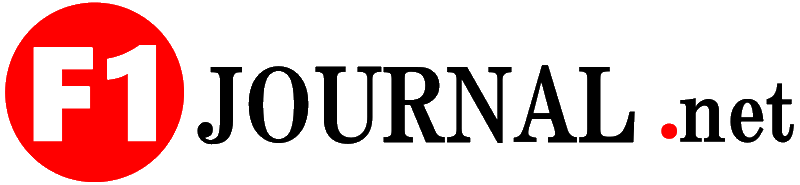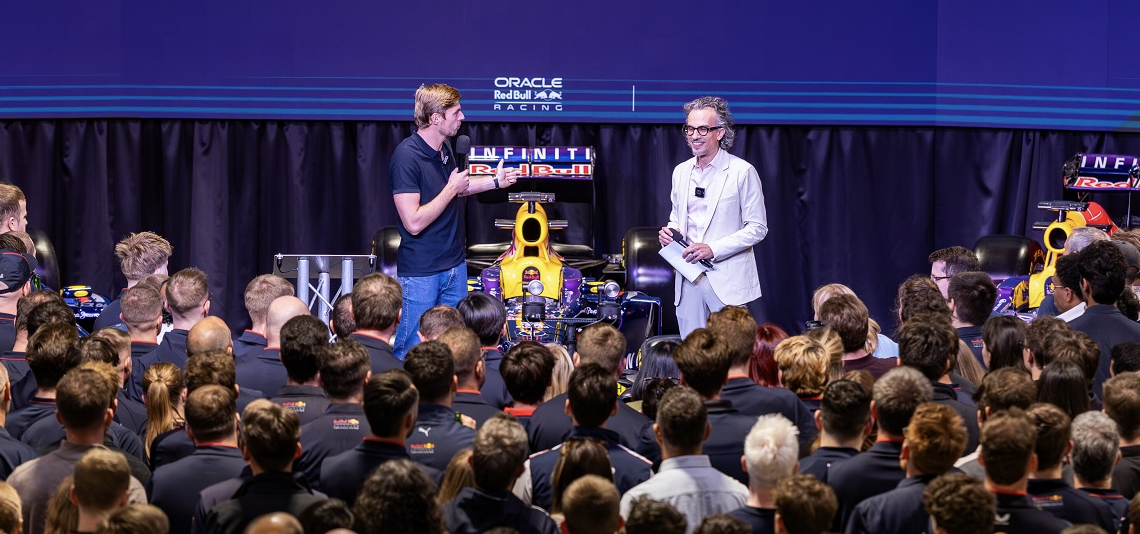2026年のF1は、アクティブエアロと電動比率の拡大により、コーナー手前の荷重変化が現状とは変わる。鍵となるのは、「ストレート用の低ドラッグ”Xモード”」と、「旋回用の高ダウンフォース”Zモード”」を切り替える分割エアロモードだ。
従来は最高速到達とブレーキングがマシンの最も厳しい瞬間だったが、電力配分に制約がある2026年仕様では、最高速が直線の数百メートル手前で頭打ちになり、終端での速度はやや落ちる。さらに減速と同時にエアロが「Zモード」に戻ることで一気に荷重が増し、ここに新たな荷重発生のピークが生まれる。
ピレリはこの変化に合わせ、タイヤ構造を刷新し、化合物や空気圧設定の見直しで戦略の幅を狙うという。規則上は前後翼を能動的に制御し、直線は「Xモード」、コーナーは「Zモード」へと全車が自律的に遷移する設計で、DRSの代わりに電力の“手動オーバーライド”が用意される。結果として、直線後半では電力が尽きて加速が鈍り、ブレーキと同時に空力が一段強まる“二重のステップ荷重”が発生する。この状況は摩耗・発熱・フラットスポットの管理を難しくし、ブレーキバイアスやエナジーマネジメント、エアロ切替点のキャリブレーション最適化が勝敗を左右するという。
ピレリの試算では最高速到達はブレーキ約300m手前に移る可能性が高く、臨界点のずれがセッティングに影響を及ぼす。2026年の狙いは軽量化と機敏さ、そしてアクティブエアロの標準化だが、分割モードの“切り替えの瞬間”は新時代の難題となる。
開幕直後は各チームの学習速度がレースの様相を変えるだろう。観戦の視点でも、ストレートエンドでの駆け引きが見どころだ。